本写真集は1976年に出版された「内海正写真集」を縮刷復刊した物です。旧来よりご遺族と親交があった写真家の髙木松寿氏からの依頼でmomentから
出版させていただく運びとなりました。内海氏は昭和39年にシュピーゲル写真家協会に入会し以後、数多くの写真作品を制作し1976年、氏の没後に
この写真集は出版されています。収録された写真はこの時代を強く感じさせるもので
非常にフォトジェニックであり同時に実験精神に富んだ前衛的アプローチは戦前からの大阪写真の流れを汲むものであると理解する事ができます。
巻末には内海氏の死を悼んで棚橋紫水氏が惜別の辞を寄せています。
collection of works
Publication September-December 2022


ASHIO ハヤシシゲミツ A4判40頁
足尾は銅山の町として知られる。 1973年の閉山後、足尾銅山観光などを 中心に観光地として、また晴天の渡良瀬川の河原 には水辺で楽しむ人々で賑わいを見せている。 車を停めてひと気が少ない商店街を進む。 渡良瀬川のせせらぎ、鳥の声。 かすかに聞こえる地方局のラジオ。 懐かしい匂い。そこに今も暮らす人々の気配。 そして失われた時間の痕跡。 8月の足尾は気温25°Cと過ごしやすく 撮影は夕刻まで続いた。
2022年8月6日 足尾にて
2022-12-06 16:24:14


WE SHALL BE RELEASED タカギトオル B4判32頁 糸綴じ製本
俺な、世の中のだいたいのひと しょうもない常識とか固定観念みたいなもんに 囚われてさ、もっと自分を開放してさ、主張すればいいと思うんよな。 と彼は言う。Y氏68歳。自分の写真で本を作りたいと言うので週末に 生家を改造したBARで店主をしながら朝から飲んだり歌ったりしている 彼の秘密基地みたいなところで撮ることにした。
キャプションより抜粋
2022-12-06 17:13:20


角谷昭二 1976 As a golden age A5判24頁
神戸の春日野道商店街。阪急の駅近くに、のぞみ青果店はある。青果店といえば野菜や果物を扱うお店と思うのだが、実際は個性強めの居酒屋的なお店であり、初めて訪れた際に店内で飼われているウズラを眺めながら一杯やるのはなんともいえない感覚でどこか懐かしいものであった。さてなぜ、のぞみ青果さんの紹介なのかというと今回紹介する写真家、角谷昭二さんはこの店の店主であるからだ。名門神戸高校の写真部の部長という経歴を持つこの店の大将は店内に高校時代に撮影した作品を壁一面に張り巡らせていた。そこに写るものは青春の群像であり、卒業アルバムをめくる時のような少々の照れくささと、ともに押し寄せるこの時代に対する憧憬。昭和、平成、そして令和。時代を超えて出現した傑作写真集。ぜひご覧いただきたい。
文 ハヤシシゲミツ
2022-12-06 17:31:34


TOKYO 1961 高木松寿 A5判72頁 無線綴じ製本
日本がまだ貧しかった昭和30年代。街中で光り輝いていたアメリカ車。 これらの写真は60年前、中学生だった私が父親の写真機を借り東京中野 の自宅周辺で撮ったものです。1964東京オリンピックに向けて都心部 は工事に伴い喧騒に満ちていました。しかし、中野あたりはまだまだの どかな武蔵野の面影を残していました。これらのクルマと背景に、時代 を感じ ていただければと思います。 作者キャプションより。
2022-12-06 17:41:27


THE END OF THE NATION イヌイジュン A5判60頁
伝説のパンクバンドTHE STALINの元ドラマーで現在もミュージシャン にして建築家、そして画家でもあるイヌイ氏の複合的な視線でとらえら れた写真集。momentで編集、デザインをお願いしているタカギトオル 氏の紹介によりmomentから出版していただく運びとなりました。 イヌイジュンTHE END OF THE NATION A5判60ページ 下記の作品紹介文はタカギトオル氏のFacebookページから引用。 「政治家と結託して」作られていく「真新しい建築物」に興味が失せた と本文で語るアンチバシーに満ちたイヌイの視線は、わざとらしくなく 経年を醸しながら佇む街角や、人が住み日々の営みのなかで朽ちていく 古家に注がれる。通りすがりにiPhoneでイッパツ」という写真群だが、 ただ表層的な「いい風景」というだけではない、風刺精神と審美感覚が 底流にある秀逸なスナップになっている。 11/26から阿佐ヶ谷ギャラリー白線にて開催されるイヌイジュンの画展 「On Sunday Morning」にて販売開始です。
2022-12-06 17:55:40


病棟徘徊「7平米のセカイ」ハマダユキヒコ B5判36頁 無線綴じ製本
ハマダさんがSNSに投稿するモノクロームの風景写真はとても味わい深く同 世代の心に響くものがある。momentを立ち上げるにあたり私はハマダさん の作品集が観たいと思ってお声がけさせてもらったところ快諾していただい た。打ち合わせを重ねているといくつかのシリーズが浮かび上がったがその 一つが病棟徘徊である。ハマダさんが一作目にこのテーマを選んだ事には少 し驚いたが、完成した作品集を拝見してとても納得。そこに広がる世界は病 棟という小さな宇宙であった。以下作者のステートメント。 ある日身体に起こった異変は、体が自分の組織を攻撃してしまうという奇妙 な病気だった。病室だけが世界のすべてだった当初からやがて病棟内を自由 に歩けるようになり退院するまでの49日間の記録。
2022-12-06 18:03:15
Publication - 2023


エリトリア 浅田トモシゲ B5判64頁
エチオピアとの30年にもおよぶ戦いの後、93年春に独立したアフリカの小国エリトリア。
その後も2018年の和平成立まで国境紛争の続く中、
2006年の夏、私はエリトリアの地に降り立った。
イタリアの植民地でもあったエリトリアの街並みは古き良きヨーロッパを思わせていて、
独特の淹れ方をするエスプレッソをポップコーンとともに振る舞うのが
客人に対する一番のおもてなしだということだった。
乾いた大地のあちこちには、かつてこの地に移住してきた
イタリア人によって植えられたサボテンが現在も植生していて
子供たちはその実を収穫し、道端などで売って家計を助けている。
「インジャラ」と呼ばれるエリトリアや周辺の国々の主食は
酸味の強いピザ生地のようなものを、
スパイスのきいた羊のモツや野菜などをつけあわせに食すのだが、
癖が強くて私の口には合わなかった。
植民地時代の面影と、アフリカの大陸的な風景が共存し、
長い紛争から復興途上のけっして裕福とはいえない生活のなかで
子どもたちの瞳は、希望と平和な未来に向けて輝いていた。
ステートメントより
2022-12-20 15:33:58


Red Photography2023 Red制作委員会 48頁カラーA4無線綴じ
本作品は神戸にあるGallery senで赤をテーマにした企画展Redで過去7回の開催で出展された作品から、Red制作委員会によって選ばれた26名の作品が掲載されています。新年にふさわしい紅白の装丁はタカギトオル氏によるデザイン。参加者26人のそれぞれの赤。是非お手にとってご覧いただきたく何卒よろしくお願いいたします。
2023-01-04 19:30:04


New York1991 ハヤシシゲミツ A4判40頁
1991年夏、ロングアイランド大学でひらかれたマスターフォト ワークショップに参 加するために ニューヨークを訪れた。マ ンハッタンに一週間ほど滞在していた時に撮影したものを写 真集にまとめました。初めての海外旅行ということに加えニュ ーヨークの街は見 るもの全てが魅力的で 興味のある対象を見 つけるとシャッターを切った。特にカメラを持った私に現地の 子どもたちは興味津々で 自らポーズをしてくれたり笑顔を作 ったりしてくれたのはいい思い出として残ってい る。
ホームレスにもよく声をかけられた。 食事をして飲食 店から一歩外に出ると必ずといっていいほどホームレスがつい て来 る。 釣り銭の小銭をめぐんでくれというのだ。小銭を渡 すと側で見ていた別のホームレ ス が次から次に近寄ってくる。あいつにやったんだったら俺にも くれよという。 ひどい時は5、6人に後をついて歩かれたこと もあった。 その年のアメリカは湾岸戦争の影響下で職を失っ た人が溢れている時期で、 日米貿易摩擦という言葉 があったように日本人の旅行者は好意的には見られてはいな かったと思う。 マンハッタンでの体験を簡単にまとめれば アベニューを 歩けば華やかなで、ストリートを歩けばそこに暮らす人々の生活感を 知ることができた。少し危険な気配も楽しみな がら撮影できたのは貴重な経験になったと思う。
長年押し入れの中に眠っていたネガからセレクトされた37枚の 写真。これらの写真を改めて眺めていると 滞在の最終日に行 動をともにしていた韓国人の玄さんとハードロックカフェで一杯 やりながら彼がリクエストした曲、レッドツェッペリンの天国 への階段が脳裏に蘇るのであった。
2023-02-03 09:36:28


MELOS 竹内彩乃
日常という不可解な世界。 MELOSというタイトルは走れメロスから引用したと竹内さんはいう。 肉体の限界、心の葛藤、障害を乗り越えて王様との理不尽な約束を果たした メロス。人間としての誠実さ強さを象徴するかのようなメロスだが 彼女からみたメロスは案外弱い一面を持つことに着目するのだという。 内面から湧き上がる自分自身が抱くイメージを一冊のzineとしてまとめています。 完全手作りで完成していた4冊は立ち上げイベントで早々完売。 次回の大阪展ではタイトルはそのままに内容を変更して制作されるとの事だ。momentに参加する作家の中で
最年少21歳の作品に注目したい。
2023-02-03 22:31:38


釜ヶ崎ポートレイト 細見大悟 A5判40頁
バンドメイトから1本の電話メッセージ、 「次のライブは三角公園、アメ村とちがうよ。釡ヶ崎。最寄りの駅は新今宮やで」 1995年の冬だった。
私は幾度となくこの街に通い演奏してきた。 音楽を通してミュージシャンや詩人、画家、映画監督などのアーティストだけでな く、
三角公園や難波屋に来ている人とも知り合い、よく話を聞かせてもらった。 そして、ライブ後飲み明かした。 とても人間味溢れる人たち、人間の強さと弱さを併せ持った激しい生き方をしてい る 人も多かった。釡ヶ崎は、マスコミだは「危ない」「怖い街」とよく言われている が
私は「やさしい街」だと思う。 それは、このまちで知り合った人たちが教えてくれた。 私は、そのように音楽を通して経験した釡ヶ崎を、知り合った人たちを写真に撮っ てきた。 ここに写っている人たちは、三角公園や難波屋でよく会う、よく知っている人たち である。
作者キャプションより抜粋
2023-02-13 22:02:08


梅田 細見大悟 A5判36頁
街にはいつも光が射す。
サラリーマンが急ぎ足で交差点を渡っていく。
高架下のバス停では、いつもの係員が乗客を案内している。
路地裏ではレストランの店員が開店前にタバコを吸っている。
いつもの梅田の朝に、光は誰にも等しく射しているいる。
けれども、光の感じ方は、話し方と同じと同じように人によって違うようだ。
写真を撮る人間にとっては、光の感じ方、光と影の選び方は、表現そのものだ。
ビルの狭間に射し込む光。アスファルトに写る影、逆光のプラットフォーム。
行き交う人々。都市に射す光と影が作る都市的な感覚。
光と影の一瞬をとらえる。
そこに生があるように思えるのだ。
2023-03-22 19:27:39


神創美鳥-exquisite- いいまゆみ
神が創造されたこの世界は人間の知恵などが及ばない創造性に満ち溢れている。
特に動物の中でも鳥の多様性の美しさには目を奪われる。
その佇まい、羽繕いの姿、視線の表情の豊かさ全てに魅了されるのである。
美しさの中に宿る命の旋律を、脈と脈の間に潜む魂の震えをその一瞬を私は捉え続けたい。
この度の作品集においては情緒豊かで美しい大和言葉からイメージした鳥の姿をまとめている。
2023-03-22 19:46:57


泡沫 うたかた/ephemeral タカギトオル B5判 108ページ 無線綴じ
人は死ぬ。花は枯れて木は朽ちる。
意匠を凝らした建造物も、
技術の粋を結集した最先端の製品も
競い合ってお買い求めされた何某も、
魂をこめて作られた美術作品も
胸に沁みるその音、その楽曲も
目を奪う鮮やかな色彩も
舌がとろけそうになるうまいめしも
感動の嵐を巻き起こす小説や言論も
愛だとか情だとか、気配やさえ
ときが経てばすべては無に帰す。
諸行は無常の理のもと
消却へと向かう現の道のりの途上で
そのはかなき姿を、刹那、とどめておく。
作者キャプションより
2023-04-19 13:08:01


Apple Town ~Nago OKINAWA ハマダユキヒコ B5判 56頁
名護市から東に進んだ東海岸に小さな集落がある。
その集落は、APPLE TOWNと呼ばれていて1959年にキャンプシュワブが 完成した時期に同じくしてアメリカ軍のHarry Apple氏が 住人達と手を取り合って築いた街だ。 ベトナム戦争 ベトナム景気の時代に、金武や古座の街と同じように 多くの米兵が足を運び300軒近い飲食店が営まれていたそうだ。 しかし、今ではその繁栄は昔の話で、今は数軒の商店やバー、 残り空家や廃屋が目立つ。
それでも、この街には不思議な魅力がある。
ボクは、そんなAPPLE TOWNに引き込まれながら シャッターを押し続けた。
2023-05-24 17:16:17


OKINAWA SIGHT SEEING 石田シンヤ A4判 36頁
沖縄を歩くと、平凡な街並みであっても何か特別な景色に見えてくる。
その特別な景色は、街に住む人達の日常であることはわかっているのだが
どうしてもシャッターを切らずにいられなかった。
東南アジア特有の熱気を帯びた湿った空気のせいではないかと考えたが
自宅のエアコンが効いた部屋で写真を見返しても
そこにあるのは見慣れない特別な景色だった。
作者キャプションより
2023-05-27 15:40:29


池島 ハヤシシゲミツ A4判 52頁
長崎市の「池島」は、世界遺産の軍艦島(端島)と
並んで、長崎県 のもう一つの主要な炭鉱の島とし
て知られています。西彼杵(にしそのぎ)半島の西側
沖合約7キロメートルの所にあり周囲は約4キロ
メートル。2001年に閉山されるまで 九州最後の炭
鉱だった池島は、無人になってしまった軍艦島と は違って、まだ人々が生活を続けています。
1970年台の最盛期には約7800人の人々が島に暮ら し、生活できるように団地群が建設されました。
世界的エネルギー事情の変化により石炭の需要は 減り2001年に閉山。地元の方の話によれば島民の
数も100人をきったという。無人化し蔦が蔓延り廃 墟化してゆく団地群はまるでオブジェのような怪
しい魅力を放っています。
炭鉱の島に残された時代の痕跡を探った2日間の 旅の記録。
文 ハヤシシゲミツ
2023-05-29 17:54:59


猫街 阿倍野編 長本淳 A5判 46頁
極めて私見だが、猫がいる街はいい街だと思う。
彼らが生きることを許容する空間と人々の温かみがある。
大阪の阿倍野もそんな街の一つだ。
しかし、老朽化で打ち壊されていく建物同様に
子孫を残せない街猫・外猫たちは消えゆく運命。
昭和以前の匂いが残るこれらの風景も、ここに住む猫たちも
近い将来には見ることができなくなるだろう。
だからこそ、今日も猫たちに「元気か?」と挨拶しに路地へと出かける。
作者キャプションより
2023-06-01 21:45:28


Nostalgia イヌイジュン
前回の政治的なタイトルから一変、今回の続編のタイトルはなんともおセンチなものとなった。
世界の終わりだ、と叫んだ半年前はまだ叫べばなんとかなるのでは、というほんの微かな希望があったのだろう。
もはやそんな希望すらない。あちら側では内外の政治のでたらめ、一方こちら側に目を向けると「弱者」や「地球環境」に寄り添うポーズの善人面したファシストだらけ。手を付けられない。ノスタルジアに浸るのは老人の悪癖。だけどもうこうなれば後ろを向かざるを得ないのではないか。アンドレイ・タルコフスキーの同名作品のようにせめて最後は故郷の森の霧や雪景色を夢みたかった。
Nostalgiaは過去への郷愁だけでなく未来への諦念の意味を隠し持っている。
本文エピローグより抜粋
2023-09-06 18:12:27


moment作品紹介其の17 空の下Ⅰ 髙木松寿 B5判モノクロ205頁
髙木松寿の写真には光と影、白から黒への世界の中に無限の時間を封じ込め静止した濃密な凝縮があり真昼の太陽も夜の闇の中に吸い取られていくような異次元の世界が私を戦慄させる。その現出した風景は、遙か彼方から続き未来永劫に普遍であるような時間を感じさせない空間として昇華され鋭利に切り取られた風景は髙木独自の精神世界を形成する。
以上の文章はグラフィックデザイナー永井一正氏が、髙木氏の作品を評したものです。
2023-09-06 19:12:20


moment作品紹介其の18 空の下Ⅱ 髙木松寿 B5判モノクロ205頁
私の作品のそのすべての原風景はいつも心のどこかにある。ある「モノ」に心を惹かれ歩み寄るときファインダーに息づく光と影は私にとって既視感の世界なのだ。心の肖像が浮かんで来たからだろうか。私はそのシーンの追体験に漆黒の闇と白との階調にすべてを託す。私は、私のモノクロームの領域で時を透明化する。
作者キャプションより
2023-09-06 19:15:10
Publication - 2024


釜ヶ崎パッション 細見大悟
釜ヶ崎では歌や音楽は皆のものだ。通りでも酒場でも歌や音楽に溢れている。
それは音楽へのパッションだ。私も三角公園のステージで演奏してきたけれど
公園に集まった人たちが音楽をとても楽しみにしていることをひしひしと感じた。
歌や音楽は、釜ヶ崎に住む人達にとって、楽しみであると同時に生きる糧、生きる力なのだと思う。そんな音楽の力、労働者と歌い手のパッションをこの写真集で記録したかった。
作者キャプションより抜粋
2024-02-26 21:07:20


猫街 西成編 長本淳
大阪に住んだことがない人間でも
一度は聞いたことのある地名「西成」。
簡易宿泊施設が集中する釜ヶ崎や元遊郭跡の飛田新地を含む
かつての濃い大阪が残る街である。
まだ無機質な高層ビルに浸食されきっていないゆえに
路上で猫に遭遇することの多い猫街でもある。
そんな西成では、時折「猫しかいない風景」に出くわすことがある。
まるで昔からそこにいたかのように
飄々と景色に馴染み佇んでいたりするのだ。
その瞬間、猫こそがこの街の真の住人ではないか、という気がしてくる。
家と家の隙間、軒下、塀や屋根の上を自由に往来する彼らは
人間よりもよほど街のことを知っている。
時代性や価値観とも無縁に、ただ逞しく健気に生きている。
ある種の羨望を覚えながら思う。
この猫たちと彼らを優しく包み込む街を
いつか消え去るであろうこの風景を
記憶に留めたいと。
作者キャプションより
2024-02-27 17:37:19


FUHEN 竹内彩乃 photozine糸綴じ製本 A5判 28P
データが消えても本は残る。そのとき感じたものを留めておける。だから本を作りたいと思った。
作者キャプションより
2024-03-13 17:27:45


残景 ハヤシシゲミツ A4判 40頁
川のせせらぎを聴きながら道を進む。 天気には恵まれたが冬の風は冷たい。
温泉街では廃業した宿泊施設や店舗の 廃墟化が進んでいる。
それらを眺めていると 自身が幼少の頃、家族と温泉地で過ごした 記憶が薄っすらと蘇る。
時代の変化とともに取り残された痕跡は 私に何かを訴えてくる。
残された景色。
それらは懐かしく
また憧憬すら覚えるのである。
作者キャプションより
2024-04-02 16:11:58


「音楽 -You Can't Always Get What You Want-」 タカギトオル B5判 96頁
本文•表紙ともに和紙にインクジェットプリント
フルカラー版/モノクロ版
制作のプロセス全て作者本人による。
撮影から編集•デザイン•印刷•製本まで
全て自家製の写真集は、2010年PX3のBOOK部門silver prizeとなった「in the real」、2011年の「on the edge」以来、実に12年ぶりの制作。ネットプリント等で手軽に写真集を作ることが可能になった時代に逆行する、全て作者本人の手により制作された写真集です。最終ページには写真集制作時に流されていた音楽のリストが記されています。
フルカラー版 ¥25,000
モノクロ版 ¥18,000
【いずれもエディション10冊のみ】
(受注生産につきご注文から納品までに約2週間かかります)
2024-04-25 13:57:14


Dis communication イヌイジュン
恥ずかしい旧式i-phoneによる写真集もついに3冊目。
今回のタイトルはこの写真集の発売と同時に開く
絵画展と同名のDis communication。
絵画はおまえとおれ、おまえとおまえ、おれとおれの関係は
全て分かり合えないのだ、とばかりに人物像で攻めてみたが、
おれの写真のテーマは都市だ。
都市が権力によってのみ立つ現代だと考えがちだが、
ヒトが権力とそして都市と決して分かり合えないのは
この時代ではなく太古の昔からである。
作者キャプションより
2024-04-25 14:00:30


diaphane 飯井マユミ 7×7インチ(EP盤サイズ)モノクロ64頁
写真集「神創美鳥」に続く待望の新作。
詩を紡ぐように心象写真を紡いだ飯井マユミ初のモノクロ写真集
2024-06-24 16:57:05


街景I、II 髙木松寿 B5版モノクロ205頁、195頁
1995年から2000年の5年間に撮影されたモノクロ写真で構成された新作写真集。
去年発表された写真集「空の下I、II」の続編と言えるだろう。
髙木氏の眼差しは光と影、また普段の生活の中で私たちが見過ごしているさりげない物や事にむけられている。ハイコントラストなプリントから浮かび上がる質感、空気感は観るものを魅了する。
2024-07-04 19:43:00


釜ヶ崎STREETノスタルジックな光と影 細見大悟A5判モノクロ32頁
路地に光が射す。人の気配、生活を感じ、匂い、街の音が聞こえてくる。
どの街にも光は等しく光は射すがその光と影、コントラストは街によって違うようだ。
光と影はその街の通りや建物、人、営み、思いをも映し出す。
作者キャプションより抜粋
2024-08-31 14:36:43


夕張 ハヤシシゲミツA4判カラー48頁
2024年7月10日快晴。
北海道旅行3日目、私は夕張にいた。 旅の目的は写真を撮る。 ただそれだけだった。
*夕張市
夕張山地と空知山地に跨る石狩炭田の南部に位置し、
かつて市域に多くの炭鉱があったが1990年までに全ての炭鉱が閉山した。
特産品の夕張メロンは全国的の有名でまた深刻な財政難は度々ニュース報道で知られたところである。
2024-09-03 17:21:53


室蘭 ハヤシシゲミツ A4判カラー36頁
輪西駅から程近い商店街を歩く。
撮影していると一人の老人に声をかけられた。
しばらくの立ち話。この街がたどった栄枯盛衰
を短時間ながら聞かせていただく事ができた。
別れ際、高台を指差し撮影にお勧めである
事を教えてくれた。勧められたとおり私は高台
に向かった。眼下には室蘭の主幹産業である
製鉄所の工場群、白鳥大橋が望めた。
対照的に私の背面には風光明媚なイタンキ浜が広がっていた。
午後からは室蘭駅から中央商店街、港を経由して
母恋まで歩いた。街中でも人は少なかったが
初めて訪れた室蘭の街はどこか懐かしく
まるで遠い日の故郷にたどりついたような
不思議な体験となった。撮影を終えて宿泊地から
程近い老舗焼き鳥店で名物の室蘭焼き鳥をいただく。
ほろ酔いで後にした店の周辺で見た景色は事情があって
一人暮らしをしていた高校時代に過ごした街の記憶と
オーバーラップするのであった。
2024年7月12日 室蘭にて
2024-09-03 17:26:49


moment作品紹介其の31「廃墟」藤井満博 A4判カラー112頁
本書は、人の手によって作られたものが長い年月をかけ自然へと渡り、本来あるべき姿ではなく
「新しいもの」へとかわっていく様を写真に収めたものである。写真家の藤井満博は
廃墟は「自然へ還る」のではなく「新しいものへと変貌をとげている」と考える。
ここにある写真はその瞬間を写したにすぎないのだ。
藤井の写真を通し、かつてそこにあった人々の営みを当時の様々な情景が染み付いたものから感じとってほしい。
そして、今もなお自然と共に「新しいもの」へとかわっていく廃墟について、是非、貴方ならではの物語をつくってみてほしい。
作者キャプションより
2024-10-02 12:08:45


PASSERBY 長本淳 A5判 モノクロ 48頁
「私たちは偶然にもこの同じ時間、空間を共有する存在である。 そして、絶えず私たちはそれぞれ時間と空間を移動していく。 長い時間の中で見れば、我々はお互いに一瞬すれ違っているだけだ。」 街に住む猫に作者自身を投影した、一種のセルフポートレート集。
2024-10-02 12:17:34


Lieu de mémoire 桜丘町 ハマダユキヒコA4判(変形サイズ)モノクロ36頁
記憶の街
1998年12月、初めて桜丘町を訪れたボクは渋谷駅西口から歩道橋を上がり、正面のビルに掲げられた巨大な壁面広告を見て圧倒された。ドラマ『神様、もう少しだけ』の登場人物である啓吾とカヲルの印象的な 姿。「やはり東京はやる事がオシャレだ」と感心しながら歩道橋を渡り、桜丘町のはずれに住む友人宅へ と向かう。
それから二十年後、再び12月に上京していた時「桜丘町の一部が再開発される」と聞いて驚き、思い出の街 を写真に残さなければという焦燥感に駆られ、訪れることにした。
街の風景は記憶とほぼ変わらないが、渋谷の外れとはいえ人影はまばらで、時雨そうな空や風に吹かれた枯葉が街の雰囲気を一層寂しくさせている。 いたるところにある工事予告の看板には、ー ヶ月後に通行止めになると書かれている。そう、この街はあと少しで姿を消し始めるということなのだ。
もし上京していなかったら、過去の記憶のままだったであろう桜丘町。最後にこの街並みと再会できたことは、悲しくも幸せに思う。
ハマダユキヒコ
●「Lieu de mémoire/記憶の街』について。
直訳「記憶の場所や思い出の場所」
Lieu de mémoireは、歴史的出来事など「忘れがたい記憶」という無形の抽象的なものを具象的に証明する有形の現実的な場所を指す。
それは、フランスの歴史学者ピエール・ノラが著書『Les Lieux de Mémoire』の中で提唱した考え。
今回のタイトルは、「忘れがたい記憶」=記憶の中にある街、「有形の現実的な場所」=桜丘町と考えた。
作者キャプションより
2024-11-01 14:56:43
Publication January-2025


自影2 髙木松寿 B5判モノクロ238頁
自影1995-2000に続く自影シリーズ第二弾。今回の作品は2001-2020年に撮影された写真で構成されている。収録された写真は234点で前作に比べボリュームのある仕上がりになっている。自らの影を被写体としそれらの背後に写る物や事は光と影が相俟って幻想的な世界観を創出している。本文中のテキストには小玉節郎氏による「影のつぶやき」が寄せられている。
2025-03-14 17:22:24


錆びたトタン板の街角で ハヤシシゲミツA4判カラー16頁
18年前に撮影されたある一人の女性の写真。
布施の街で撮影されたものである。
その16年後、偶然にもこの街を
訪れた私の脳裏には薄っすらと
彼女の姿が浮かびあがっていた。
街を歩き進めると彼女の背景に
写る街の風景の多くが
消滅し現存しないことを知る。
失われた街
過ぎ去り消滅した時間
それらは再び邂逅し
幻影を浮かび上がらせた。
2025-03-14 17:29:05
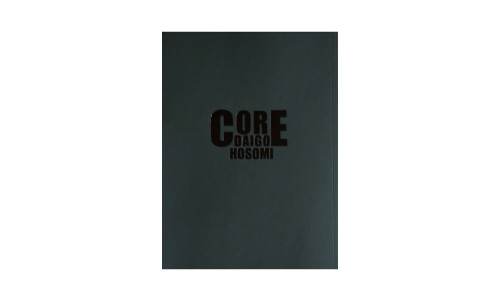
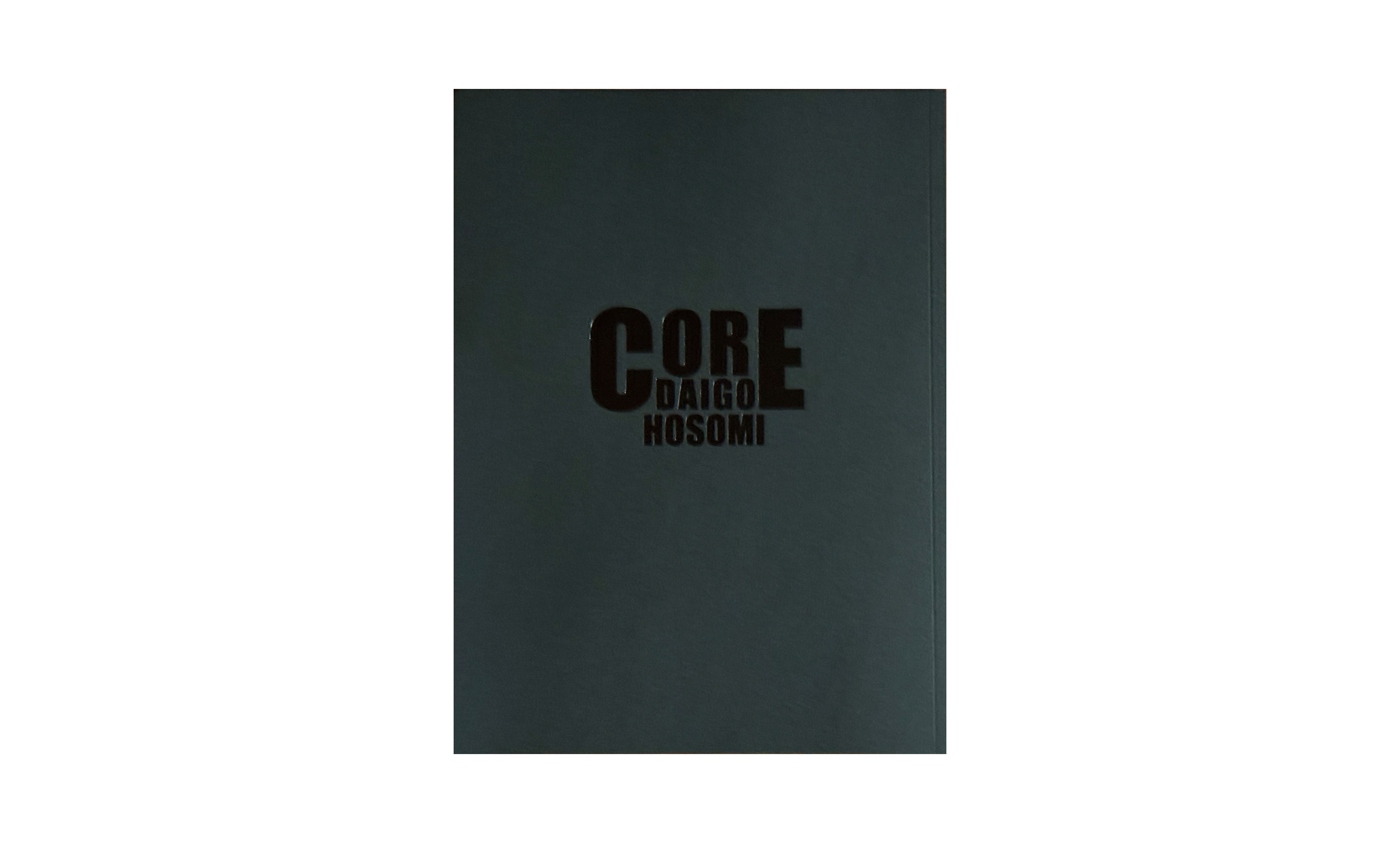
CORE 細見大悟 B5判モノクロ48頁
釜ヶ崎の立ち飲み屋、三角公園、吉田寮、ラテンCDショップからストリート、路上。
予め決まっていることはない。
全ては即興であり、予定調和はない。
私は現場に最後まで居る。
その場にいかに強く居るかが
表現の核になるからだ。
写真は、私自身のドキュメントなのだ。
作者キャプションから抜粋
2025-08-11 17:48:10


subliminal forest 山形紗織 A4判48頁
自己の潜在意識と向き合う過程で生まれてきた創作的な作品だと作者はいう。
銀塩でプリントされたモノクロームの世界からは彼女自身の内面的自己との対話であり
セルフポートレイトと花や草木の逞しい写真との対比で作者の内面にある不安や不安定さ
を表出しようと試みている。
「私は不完全なままの自分で生きることを受け入れ始めていた
それは創作という手段だからこそ叶えることのできた自己受容だった」
「」作者キャプションより抜粋
2025-08-11 18:23:00


the liminal city 山形紗織 A4判50頁
その一瞬、私の無意識は何に反応してシャッターを切らせたのか?
写ったイメージを媒介に、私は無意識の中に潜っていく。
深海の澱みを、あぶくを、そこに潜む混沌を炙り出していく。
街には数多くの人間が行き交う。寄る辺ない心持ちでファインダーを覗く、
私の目は人々の意識の海を見つめている。
フィルムを重ね合わせての合成やソラリゼーションなど、暗室技法を組み合わせて
作る創作的なイメージには、無意識と意識.作為と偶然が絡み合う。
私には、その混沌としたイメージこそリアルな街の姿のように感じられる。
作者キャプションより抜粋
2025-08-11 18:44:43
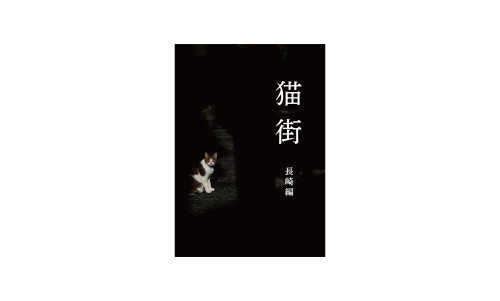
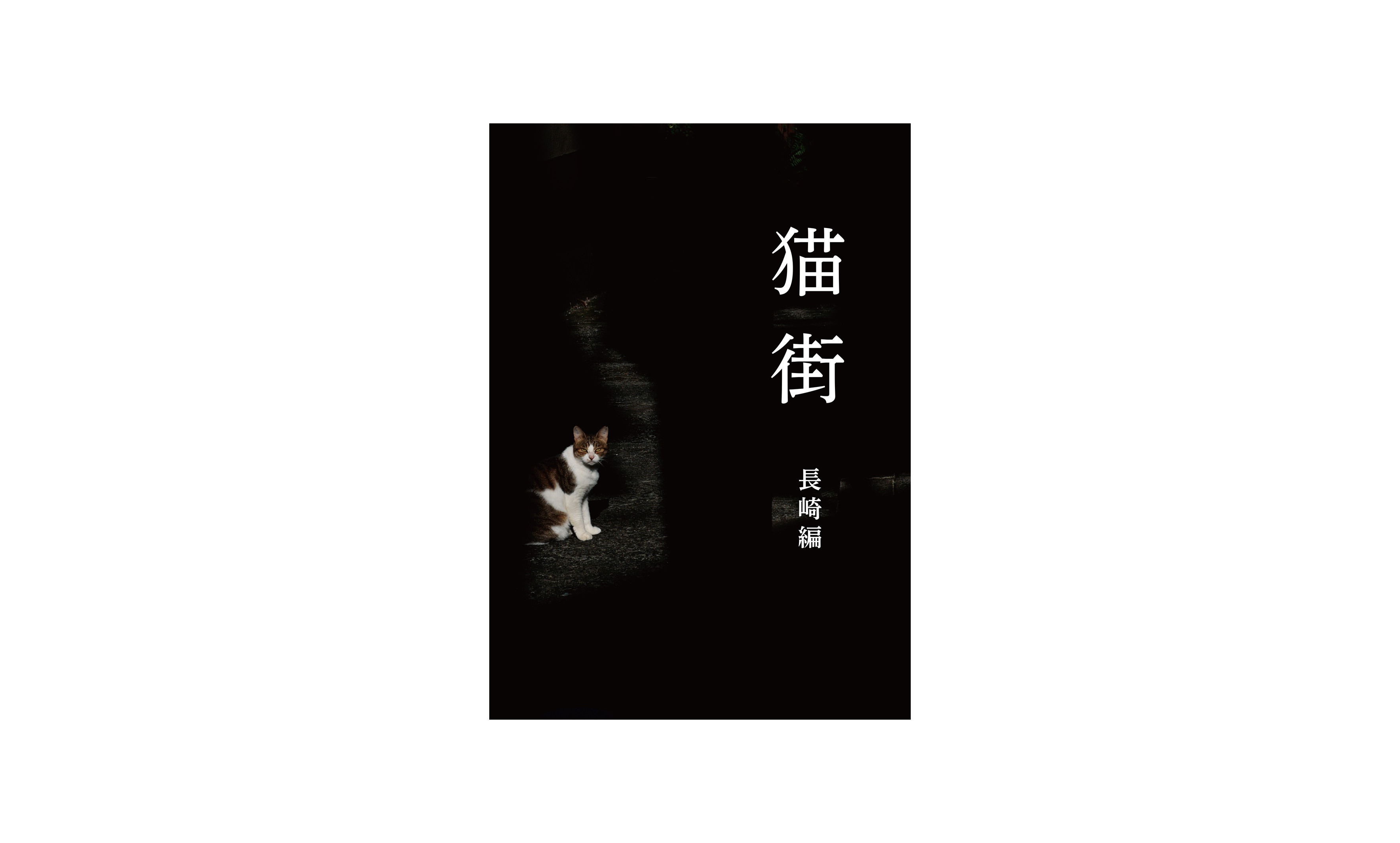
猫街長崎編 長本淳A5判96頁
江戸時代から貿易の街として栄えた長崎。
港にやってくるオランダ船には
ネズミ駆除のために猫が乗っていたという。
その末裔が血脈を伝える猫街でもある。
特に山面の古い街並みでは
多くの地域猫、外猫に出会える。
狭く迷路のような坂道は彼らにとって良き遊び場だ。
かつてのオランダ船に乗っていたのは、
東南アジアにルーツを持つ尾が途中で曲がっていたり、
先端が丸く縮まっている猫。
そのため長崎では「尾曲がり猫」が多く見られるのだそうだ。
幸運を鉤のようにひっかけてくるということで近年人気も高まっているらしい。
尾曲がりであってもなくても
猫たちが佇む姿は我々に幸せな気持ちを与えてくれる。
このささやかな幸福を多くの人たちに感じてもらえることを願いつつ
猫街長崎に思いを馳せる。
港にやってくるオランダ船には
ネズミ駆除のために猫が乗っていたという。
その末裔が血脈を伝える猫街でもある。
特に山面の古い街並みでは
多くの地域猫、外猫に出会える。
狭く迷路のような坂道は彼らにとって良き遊び場だ。
かつてのオランダ船に乗っていたのは、
東南アジアにルーツを持つ尾が途中で曲がっていたり、
先端が丸く縮まっている猫。
そのため長崎では「尾曲がり猫」が多く見られるのだそうだ。
幸運を鉤のようにひっかけてくるということで近年人気も高まっているらしい。
尾曲がりであってもなくても
猫たちが佇む姿は我々に幸せな気持ちを与えてくれる。
このささやかな幸福を多くの人たちに感じてもらえることを願いつつ
猫街長崎に思いを馳せる。
作者キャプションより
2025-08-11 19:09:12
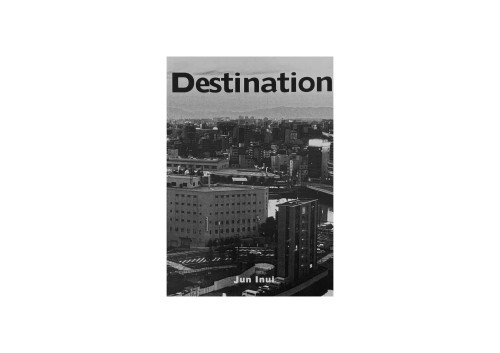
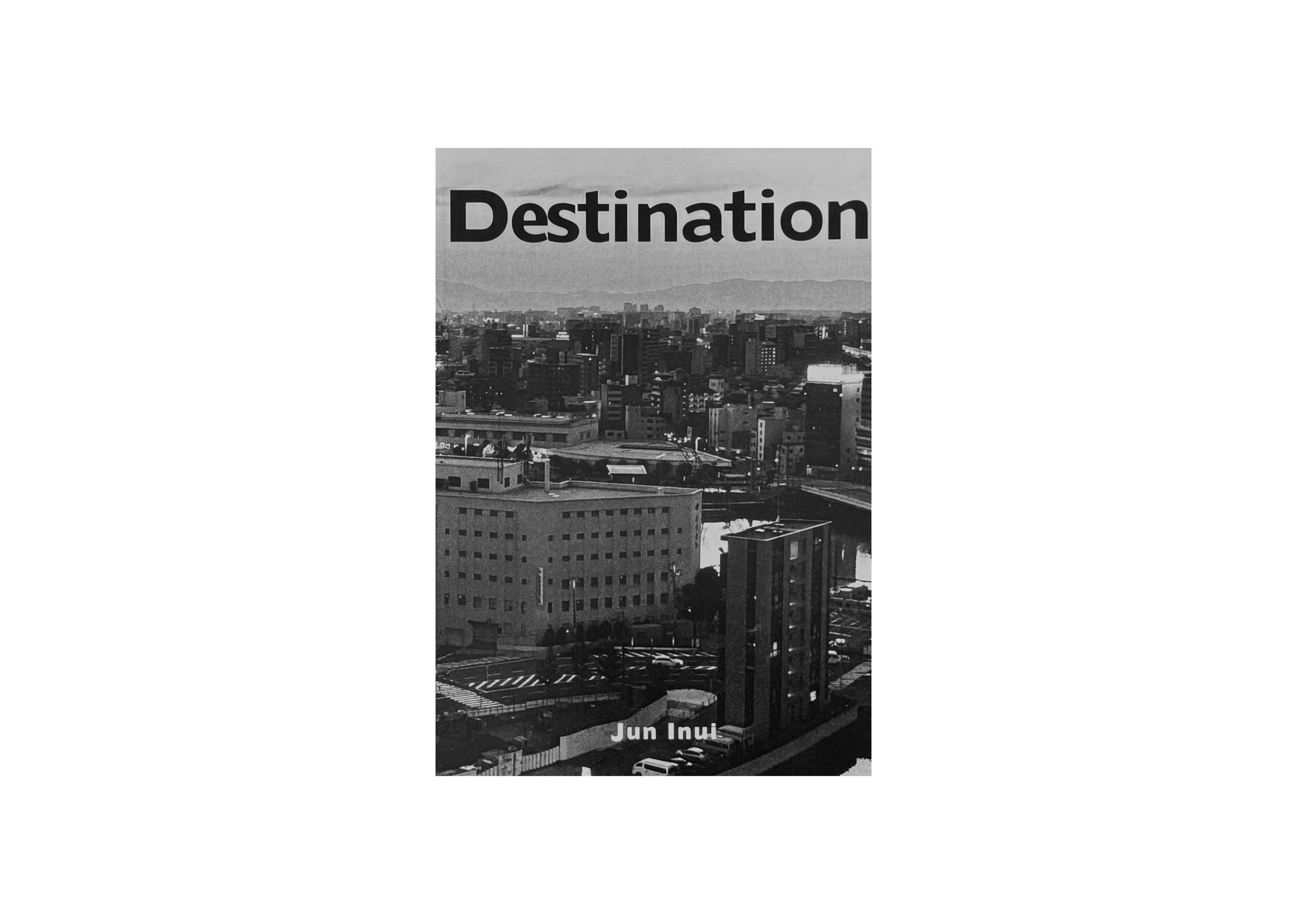
Destination イヌイジュンA5判モノクロ72頁
到着地
自由ないi移動は権力だ、という主題で絵画展を開いている。
到着地をいかに花の都に感じようがそれは所詮徒花、
金をかけて到着は絶望であるかもしれないぞという
旅なんかに金をかけられない者のやっかみ半分、
行っちゃえる奴への脅し半分がテーマだ。
そんなオレでも偶に呼ばれれば各地へ出向くこともある。
見たことのない景色に出会えばやはり写真に収めたくもなる。
やはりやっかみなのだ。
人生はしばしば旅になぞらえられ、その到着地はすなわち死だ。
心して残り少ない旅を続けることだ。
作者キャプションより
2025-08-24 17:01:47
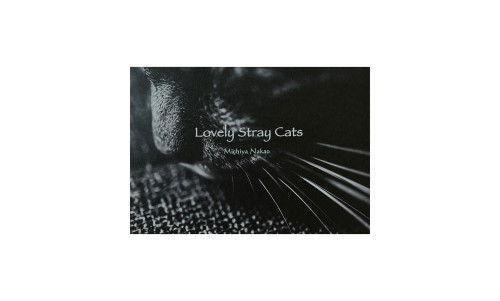
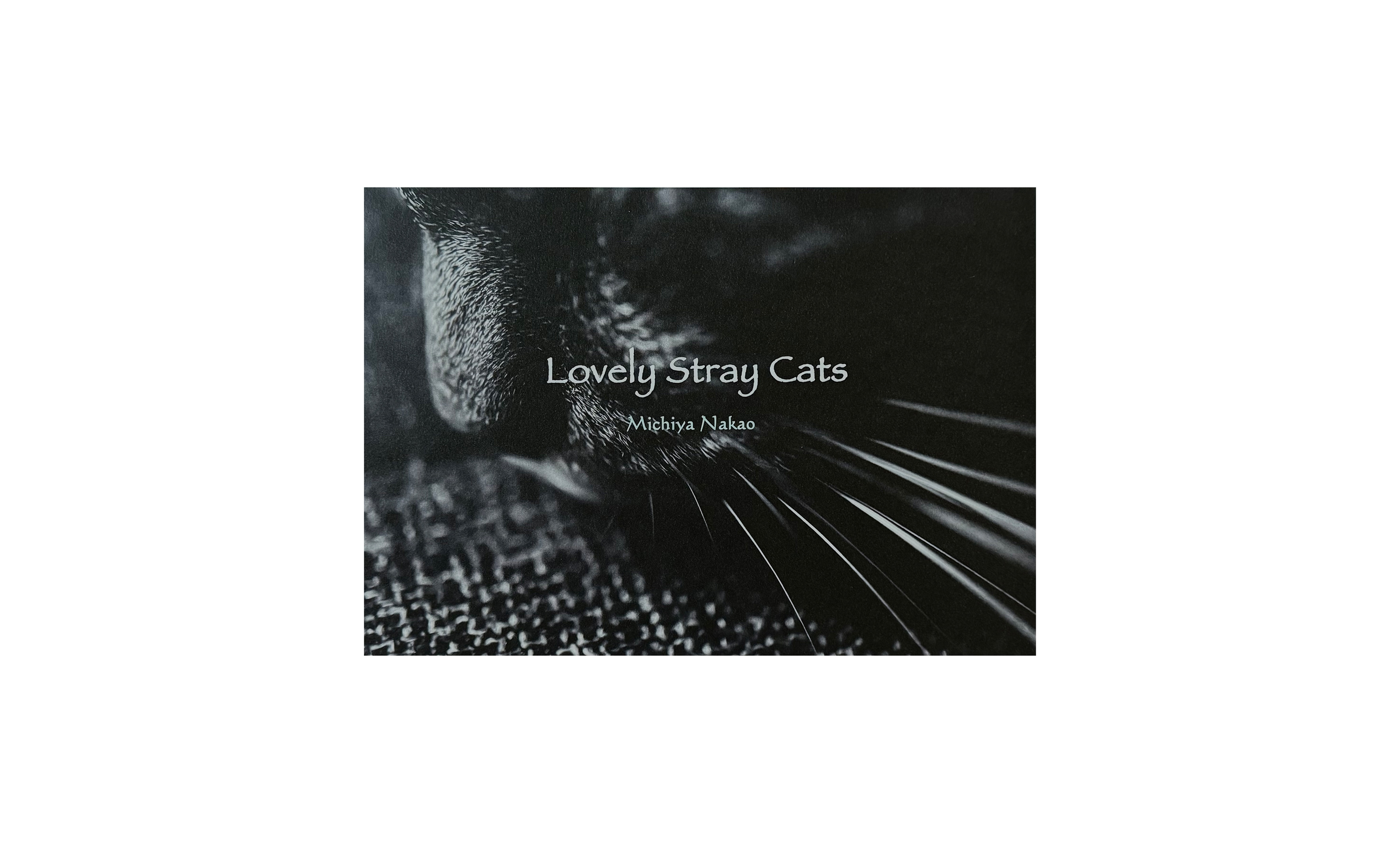
Lovely Stray Cat 中尾美智也 B5判40頁
野生の中で生きてきた野良猫の表情 の中に、自然の厳しさや、生命の儚さ 愛おしさを見つけることが出来ます。 その表情は、媚びたり威嚇したり安 らいだり、生きていくため切りかわり ます。 生命の輝く時間が短い野良猫は、私 を魅了し生命と時間の大切さを教えて くれます。
In the expressions of stray cats who have lived in the wild, I can find the harshness of nature, as well as the fleeting yet precious beauty of life.
Their faces shift - sometimes coaxing, sometimes threatening, sometimes at peace - all as a means to survive.
With their brief but radiant lives, stray cats captivate me and remind me of the true value of life and time.
作者キャプションより
2025-10-02 11:03:44
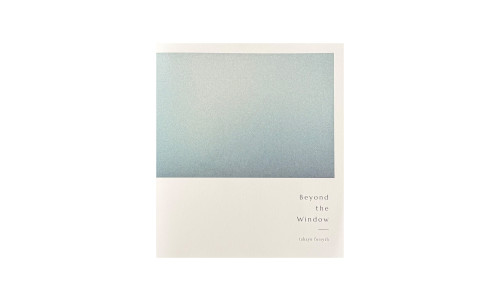
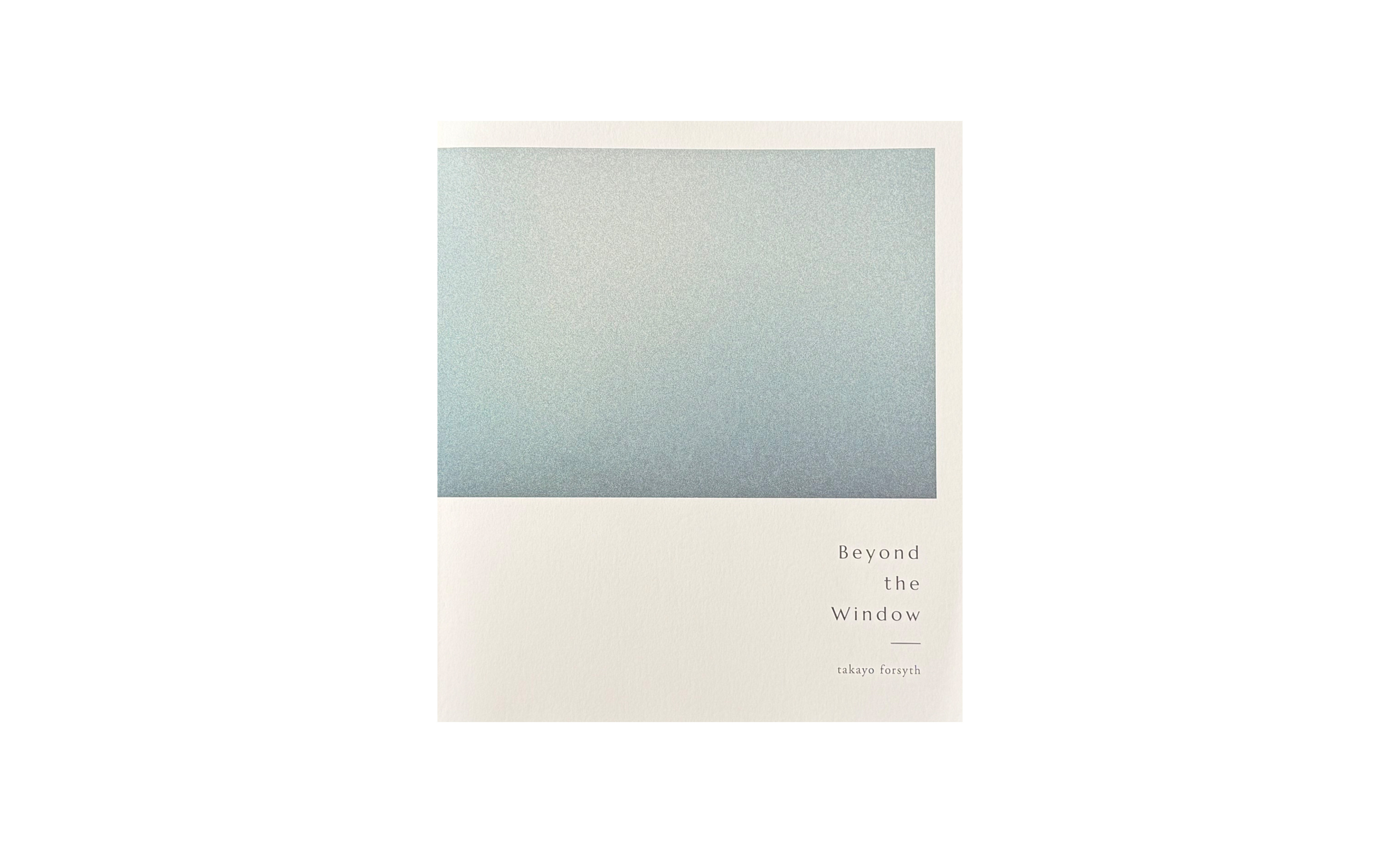
Beyond the Window フォーサイス啓予 A4判変形カラー40頁
Beyond the Window
窓の向こうには
まだ見ぬ景色が息づいている
光は影を呼び
影は記憶を深める
そのあわいに 心は静かにたゆたう
Beyond the window lies a world yet unseen.
Light calls to shadow,
and shadow deepens memory.
In that in-between,
the heart drifts in quiet repose.
作者キャプションより
2025-10-02 11:20:10


YANAGASE ハヤシシゲミツ A4判カラー36頁
時代の残景を記録する作者の
シリーズ第8弾。
新作の舞台は岐阜柳ヶ瀬。
戦後の復興から繁栄を
極めた昭和の残り香。
眼前に広がる時代の幻影。
自身の記憶の街とクロスオーバー
しながら撮影した2日間の旅の記録。
2025-10-02 12:49:05













